gtd(getting things done)はデビッド・アレンが提唱した世界的に有名な仕事術です。gtdの三つの柱を実践するとこで、生産性を上げて仕事の効率性と達成度をアップし、忙しい日々のさまざまなことをコントロールできるようになります。
2001年にデビッド・アレンがgtdを提唱した著書「初めてのgtd」は2015年に全面改訂版が出されました。
その全面改訂版の「初めてのgtd」で追加された「gtdの三つの柱」を説明しながら、gtdの基本を解説します。
gtdの三つの柱とは?アレンの著書の全面改訂版で追加された要素
gtdは、デビッド・アレンが2001年に「はじめてのgtd」で提唱した仕事やタスクの管理術です。
日本語版の「はじめてのgtd」に掲載されたプロフィールによると、アレンは生産性に関する世界的な権威として、「ニューヨークライフ保険、世界銀行、フォード財団、L・L・ビーン、米海軍などで相談役を務め」ると書かれています。
現在は、同書の全面改定版が2015年に出されており、gtdを実践する人のバイブルとなっています。
日本では、あまりメジャーではないgtdですが、英語版のアマゾンでは、この「はじめてのgtd」が、仕事術や、時間管理術で、ベストセラーの常連になっています。
gtdの意義を凝縮した「三つの柱」
改訂版「はじめてのgtd」には、2001年版にはなかった記述としてgtdの「三つの柱」が列挙されています(27ページ)。
①「1つ目は、やるべきことや気になることの”すべて”を把握することだ。いまやらなければいけないこと、あとでやりたいこと、いつかやる必要があること、、、大きなことも小さなことも、すべとを頭の中からいったん吐き出して、信頼できるシステムにあずけなくてはならない(以下、略)」
②「柱の2つ目は、人生において常に降りかかってくるあらゆる”インプット”にその場で対処できるようにすることだ。それらが発生したときに適切な判断を下し、”次に取るべき行動”を具体的かつ自信をもって導けるようにならなくてはならない」
③「柱の3つ目は、そのようにして導かれたさまざまな判断のすべてを、人生における異なる視点レベルから評価しつつ、いついかなるときでも正しい決断を下せるようになることだ」
3つの柱は、gtdを実践する際のポイントとなることを示すとともに、gtdがなぜ仕事の効率化や忙しい日常のコントロールに効果的なのか、その理由を短い言葉のなかに凝縮して示しています。
以下、柱の一つひとつについて、解説していきます。
関連記事
・gtdの三つの柱。効率性を上げ、忙しい日々をコントロールする仕事術
・gtdの5つのステップの概要~自然な思考で自分の時間を取り戻す方法
・gtdアプリnozbeの特徴、便利な点~gtdのタスク管理を自然に自動で実現
gtdの柱①~「気になること」から頭脳を解放する
一つ目の柱のポイントは
①「1つ目は、やるべきことや気になることの”すべて”を把握することだ。いまやらなければいけないこと、あとでやりたいこと、いつかやる必要があること、、、大きなことも小さなことも、すべとを頭の中からいったん吐き出して、信頼できるシステムにあずけなくてはならない(以下、略)」
でした。
ここでのポイントは、「気になること」をすべて、把握することの大切さです。
gtdでは、人間の脳を、一種のワーキングメモリーのようなものとしてとらえます。
最近のパソコンでは、メモリーが大量に積まれているので、あまりなくなりましたが、以前のパソコンはメモリー不足で処理が追い付かず、フリーズ(動作が停止)してしまう、ということがよくありました。
人間の脳にも、同じことが起きてしまうのです。
「あのメールに返信しないと」「明日が締め切りの書類があったな」といった仕事上のことから、「子どもの保育園の給食代、振りこまないと」「トイレの電球がつかないから、買い替えよう」という生活上のことまで、さまざまな「気になること」が頭の中にあると、その分だけ、ワーキングメモリーの一部を占めてしまうことになります。
gtdを実践していない人の脳は、容量に限りのあるワーキングメモリーを、多くの「気になること」が占めてしまっている状態です。
その結果、フリーズが起きてしまい、簡単なタスクの処理も十分にできなくなってしまいます。
本来、脳が使うべき能力は、「この仕事をどう処理するか」という処理能力や、「新しいアイデアを生み出そう」という創造力なのに、そのためのメモリー容量が「気になること」の記憶保持能力のために浪費されてしまっている、ということです。
インボックスを使って、すべての「気になること」を集める
gtdでは、こうした脳のメモリーのフリーズ状態を防ぐために、「気になること」を「インボックス」と呼ばれる、受信箱に集めます。
書類も、メールや電子データも、備品などの物も、アイデアも、「気になること」が生じたら、すべてとりあえず、それぞれに合わせたインボックスに集めていきます。
これにより、頭のメモリーが「気になること」の保持から解放されたら、どれだけの処理能力や創造力が発揮されるか、gtdを実践してみると、驚くはずです。
私自身は、gtdを初めて実践し、「気になること」を頭からすべて吐き出した時(書き出したタスクやアイデアだけで234個以上、整理されていない書類やメールがその他にも大量に出ました)、「こんなにたくさんの『気になること』を抱えながら、よくこれまで仕事をしていたものだ」とあきれる思いをするとともに、頭の中にぼやーっとかかっていたカスミが、すっきりと晴れて頭脳が働きだす、そんな感覚を覚えました(自分の頭脳がカスミがかかった状態だったということ自体、gtdを実践後に初めて気づいたことですが)。
gtdの柱②~本当に必要な行動を見極める
gtdの二つ目の柱は
②「柱の2つ目は、人生において常に降りかかってくるあらゆる”インプット”にその場で対処できるようにすることだ。それらが発生したときに適切な判断を下し、”次に取るべき行動”を具体的かつ自信をもって導けるようにならなくてはならない」
でした。
ここでのポイントは、インボックスに集めた「気になること」をどう処理するか、です。
人生においては、常にさまざまな「インプット」が生じます。
上司や取引先からの連絡や仕事の依頼、進めていた仕事に発生するトラブル、テレビを見ていたときに浮かんだ使えるかも知れないアイデア、家の冷蔵庫が突然に壊れて買い替えが必要になること、などなど。
こうした様々な「インプット」の内容に応じて、何か行動をとる必要があるのか、とるとすればどういう行動が必要か、いつどんな手段でやるのか、判断する必要があります。
1つ目の柱で書いたように、gtdでは、多くのインプット=「気になること」は、とりあえずインボックスに集めます。
インボックスのなかに、「Aさんからの依頼の書類」、「冷蔵庫が壊れた」などのメモやタスクを入れておくことになります(簡単なタスクの場合、あるいは逆に緊急性が高い場合、その場で判断し、行動に移すことも、もちろん多くあります)。
そうしてたまったインボックスから、「気になること」を一つ一つ取り出し、「どういう結果が求められているか」「そのために、どういう行動が必要か」という二つの観点から、その「気になること」について判断を下すのが、「見極め」と呼ばれるステップです。
タスクを処理する前に、とるべき行動を決める(行動するのかしないのか、いつどんな手段でどんな行動をするのか)プロセスを重視するということです。
「見極め」を行うと、目の前にある「気になること」の背後に、思いもよらないような課題が隠れていることがよくあります。
例えば、「気になること」が「Aさんの依頼した書類をつくる」だったら、書類をつくればよい、多くの人はそう思います。
しかし、実際は、その書類をつくるには、来年度の事業計画を練り直す必要があり、そのためには、事業計画のポイントとなるBという計画について、Cさんの意見を聞く必要がある、という場合はよくあります。
つまり、いま取るべき行動は「書類をつくること」ではなく「Cさんの意見を聞くために、アポを取ること」です。
こうした「気になること」の背後にある、本当のやるべき行動を判断するのが、「見極め」です。
gtdと通常のタスク管理との違いは「見極め」を重視すること
タスク管理というと「todoリスト」の作成が有名です。
私自身、gtdを実践する前、何度もtodoリストを作成しました。
todoリストを作った直後は、仕事がはかどるのですが、日々、起きる「インプット」によって、達成されていないタスクがどんどん増え、todoリストは長く膨大になり、機能しなくなっていきます。
それは、先ほど書いたように、「見極め」をせずに「気になること」をそのまま、リストに並べただけのtodoリストは、「本当に必要な行動」のリストにはなっていないからです。
gtdを実践することで、こうしたtodoリストに並ぶ膨大な「気になること」を、先に書いた二つの観点から見極め、本当に必要な行動を判断し、実行に移していくことができるようになります。
関連記事
・gtdの三つの柱。効率性を上げ、忙しい日々をコントロールする仕事術
・gtdの5つのステップの概要~自然な思考で自分の時間を取り戻す方法
・gtdアプリnozbeの特徴、便利な点~gtdのタスク管理を自然に自動で実現
gtdの柱③~異なるレベルの視点からタスクを評価して次の行動を決定する
三つ目の柱は
③「柱の3つ目は、そのようにして導かれたさまざまな判断のすべてを、人生における異なる視点レベルから評価しつつ、いついかなるときでも正しい決断を下せるようになることだ」
でした。
ここでのポイントは、「見極め」によってつくられた、「必要な行動」のリストから、その時々に何を選び実行に移していくかの判断です。
リストに並ぶのは、すべて必要な行動でも、その時に与えられた時間や、場所、条件、さらには自分の精神の状態などで、なにを選び実行していくのかは、変わってきます。
その基準も、gtdによって身に付けることができます。
ボトムアップとトップダウンのタスク管理の視点を組み合わせる
3つ目の柱の文章にある「人生における異なる視点レベルから評価」というところが、非常に大事な点です。
仕事術というと、まずは「人生の目的」を考え、「そのために必要な目標」を決め、「達成のためのプロジェクト」を決めて「そのためのタスク」を優先して実行する、といった「トップダウン型」の考えを持ちがちです。
一見すると、とても効果的な方法に見えますが、実際はうまくいかないことが多いでしょう。
たとえ「人生の目的」のために「今やるべきタスク」がわかっても、日常生活の忙しさがコントロールできていなくては、それらの日常の「気になること」に追われて、手を付けることができないからです。
大切なのは、「異なる視点レベル」をミックスすることです。
つまり、日常の「気になること」から必要な行動を見極め、そうした行動の積み重ねのなかで必要になるプロジェクトを設定していく、というボトムアップの考え方と、先のトップダウンの考え方の両方を組み合わせること、です。
特に、さまざまな視点レベルのなかでも、gtdでは「プロジェクト」レベルの視点を重視します。
このプロジェクトという言葉のとらえ方も、gtdでは、一般の用語法と違うところがあります。
gtdでいうプロジェクトとは、「達成までに複数の行動が必要な『望んでいる結果』」と定義しています(「はじめてのgtd」73ページ)。
「来年度の事業計画の作成」「新人社員の採用」といったものから、「パソコンの買い替え」、さらには「娘の入学の準備」「部屋の模様替え」といったことまで、さまざまなものが考えられます。
gtdでは、自身の抱える、こうしたプロジェクトを並べた「プロジェクトリスト」も作成します。
週一度など、折に触れてプロジェクトリストを見直すと、プロジェクト達成のために必要なのに忘れていたタスクや、必要になっているけど手を付けていないプロジェクトが、必ず浮かぶはずです。
これにより、仕事や日常生活の未来を先読みして、早め早めに必要なタスクに取りかかることができるようになります。
gtdの3つの柱を実践することの効果は?
gtdは仕事術と分類されることが多くありますが、通常の仕事術とは違い、仕事上のことからプライベートのことまで、日常のすべてをgtdというシステムで監理しようというものです。
3つの柱は、気になることを書き出したり、そこから必要な行動を見極めたり、さまざまなレベルから判断して行動を選んだり、実は多くの人が日常的にやっていることでもあります。
gtdは「大量の仕事」へのワクチン
gtdのポイントは、それらをシステムとして確立し、徹底的に、あらゆる分野でやる、ということです。
こうしたgtdの考え方が分かっていると、日常のいろいろな場面に応用することができます。
私自身が以前そうであったように、「いくらやっても仕事が終わらない」、「頭がやるべきことであふれて、いっぱいいっぱい」という人にこそ、特におすすめな仕事術です。
アレンの「はじめてのgtd」には、アレンのクライアントのこんな言葉を紹介しています(23ページ)。
gtdを習慣にすることで「人生が楽になる」
「gtdを習慣にしたら、人生が楽になりました。本気でやりだしたら、人生が変わりました。たとえて言うならば、毎日の大量の仕事に対抗するためのワクチン、多くの人が陥っているジレンマを解消する解毒剤なのです」
この言葉は、私自身の実感でもあります。
gtdをやっても、日常の仕事がなくなったり、減ったりするわけではありません。
むしろ、仕事を効率的にこなせるようになると、周りの信頼が高まり、さらに多くの仕事があなたに期待されるようになるでしょう。
しかし、仕事や生活のさまざまな「気になること」への対処の方法を知ることで、忙しさをコントロールし、どんな忙しさの中でも自分の時間を取り戻すことができるようになるのが、gtdの効果です。

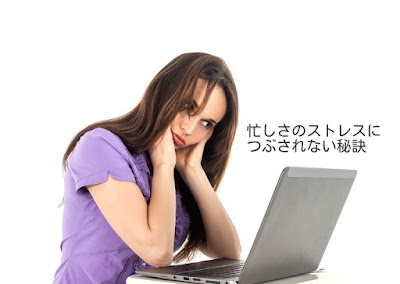




0 件のコメント:
コメントを投稿